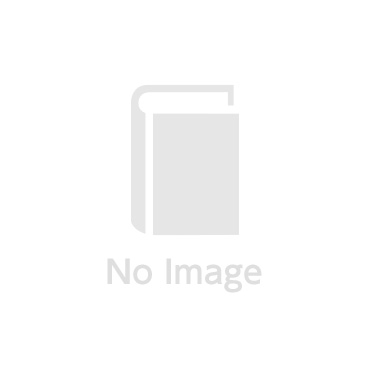尖閣問題に関する我が国政府の基本的立場は「尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上からも明らかであり、現に我が国はこれを有効に支配していることから、領有権の問題はそもそも存在しない」というものです。
中国側も領有権を主張していますが、これまでの中国側の主張には合理的な根拠を見いだすことはできません。そのため、中国が尖閣諸島の領有権主張の御旗を掲げ続ける唯一の拠り所は、日中国交正常化交渉の際に首脳間で約束したという(領有権棚上げ約束論)しか見当たりません。
それにもかかわらず、尖閣諸島周辺のわが国領海では、海上保安庁と海警局という、共に海上警察機関同士が法と正義を掲げて互いに一歩もひかず一触即発の緊迫した攻防を繰り広げています。
これは、中国が日本の有効支配を切り崩し、やがて尖閣問題を日中間の領土問題としていくという、中国のねらいどおりの展開になっており、日本側は中国の「罠」にすっかりはめられているように見えます。
中国は、中国海警局が海上警察機関であることを裏付け、国際社会からの批判をかわすために(中国海警法)を制定しました。同法は、中国海警局が人民武装警察の傘下の海上部隊であることを明記しています。そして海警局には、同法に基づき外国の軍艦や政府公船に対しても武器使用などの強制措置を執る権限が与えられています。さらに、中国海警局は、軍事機関としての任務も付与されたうえで、人民解放軍と共に中国共産党軍事委員会の指揮下に組み入れられました。
一方、これを機に我が国国内では、警察権に基づく武器使用に際しての危害要件を緩和すべき」とか「海上保安庁に軍事的な役割を付与すべき」といった議論が沸き起こりました。しかし、こういった冷静さを欠いた発想こそ中国側の「罠」にはまってしまうことになりかねません。海警船は、これまでも不法侵入を繰り返していますが、今後は突然軍事行動に切り替えてきたりすることも予想されます。しかし、だからと言って海上保安庁にせよ自衛隊にせよ現場での実力によって対処しようとすれば武力衝突その他の不測の事態に発展する可能性が高くなるばかりです。したがって、今の日本にとって、中国から尖閣諸島を守るためには政治的・外交的に責任ある取り組み抜きには考えられないが、その動きはほとんど見えてきません。むしろ、現場に「下駄を預けっぱなし」にしてきたのではないかと思えてなりません。
実際、海警法施行後もこれまでどおり対処責任を海上保安庁に託し続けています。今の日本は、それ以外に選択肢がないのかもしれませんが、それも”戦後”から脱却できないままの今の日本を象徴しているように思われます。
では、海上保安庁はこれからどのように対処すべきか。また、我が国はそのように対応すべきか。
そこで、本書では、中国海警法の概要とその問題点を見極め、尖閣問題の原点に立ち返ってその発端からこれまでの経緯を振り返ったうえで、今後の海上保安庁の対処のあり方並びに我が国の対応と事態の打開策について検討課題と併せて提言することにします。