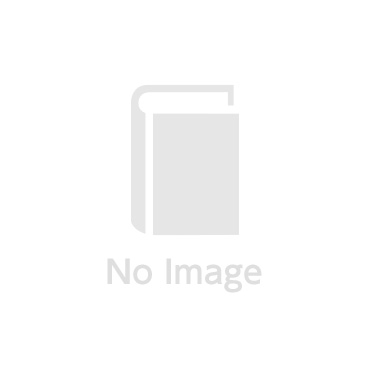本書では,PFI(Private Finance Initiative)など官民連携事業(PPP=Public Private Partnership)の役割を経済学的な観点から多角的に考察した.国と地方の財政赤字の累積や少子高齢化が益々深刻となる中,限られた予算で,既存のインフラ老朽化の問題を解決し,より良い行政サービスを維持していくことは,喫緊の課題になっている.そのようななか,新しい行政経営(ニューパブリックマネジメント)の手法であるPFIなど,官民連携事業の役割がこれまで以上に注目されるようになっている.
しかしながら,先行して官民連携を推進した英国などで失敗事例が数多く存在することからもわかるように,官民連携によって常に公共事業の効率化が図られるという発想は短絡的である.官民連携のあり方は多種多様であり,それを導入・推進する目的は,私的利潤の最大化に基づく財・サービスの供給とは本質的に異なる.そこで,本書では,官民連携事業を導入することでどの程度財政負担が削減できるかに注目する従来の視点を改め,どのような環境の下で官民連携が有効に機能するのかを理論的に考察した。さらに,「仙台空港コンセッション事業」や「大阪城公園パークマネジメント事業」の事例研究に加えて,わが国でこれまで行われた官民連携事業のパネルデータを用いた実証分析から,理論モデルの妥当性を論じた.
具体的には、どのような環境の下で官民連携がうまく機能するのかを,2つの大きな視点から考察した.第1が,「プリンシパル・エージェント理論」を用いて,事業のガバナンス構造を考察する視点である.官民連携は,官=依頼人が民=代理人に業務を委託するプリンシパル・エージェントの関係として捉えることができる.本書では,非効率性を発生させないために,官民連携において,民のインセンティブを高める報酬体系を設定することが重要となることを指摘した.第2が,PFI事業を委託された民が,複数の事業を同時に行うことによって発生する「シナジー効果」に注目する視点である.PFI法改正により「コンセッション方式」の導入がなされ,多くのPFI事業で委託された民が,自由度高く官民連携事業を運営することが可能となった.本書では,そのことで供給サイドと需要サイドの両面からシナジー効果が生まれる余地が大きく高まったことを指摘した.
これらの考察を通じて,わが国の官民連携事業のあり方に,経済学的観点から新たな見方が加えられたといえる.