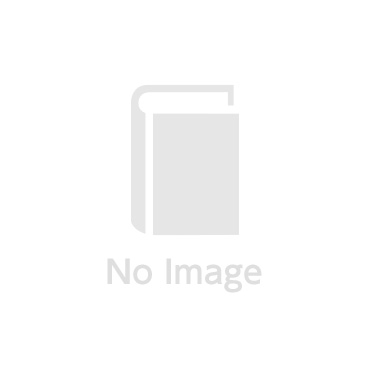序章
§1 上代語には終止形「見る」はない
§2 「見」の終止形は上代語では「み」である
§3 上代近畿語・上代東方語・上代九州語は同等に貴重
凡例
第一編 「見」の終止形が上代語で「み」になる理由
第1部 動詞連体形の活用語足はAU
第1章 動詞連体形の活用語足はAU
§1 音素・語素
§2 音素節・母音部・潜化・顕存・融合
§3 父音素・父音部・母類音素・完母音素
§4 近畿語完母潜顕法則
§5 本質音・現象音
§6 四段活用動詞連体形語尾の母音部はAU
§7 動詞の六活用形は活用語胴と活用語足に分解できる
§8 四段動詞の直結形
第2部 Yは「い甲」を形成する
第2章 Yは「い甲」を形成する音素の一つ
§1 近畿語で「ヨ」にも「イエ」にもなる「良し」の第一音素節はYYO
§2 兼音素・父類音素
§3 「います」の「い」はY
§4 動詞に助動詞「ます」が続く用法は語胴形Yます用法
§5 Yは「い甲」を形成する音素の一つ
§6 「ゐやぶ」の「ゐや」が「うやうやし」で「うや」になる理由
第3部 双挟潜化
第3章 「行く」が「ゆく」とも「いく」とも読まれるのはどうしてか YUY
§1 双挟潜化
§2 「行く」第一音素節が「ゆ」とも「い」とも読まれるのはどうしてか
§3 形容詞「斎斎(ル ゆゆ)し」 YUYYUY
§4 上代語「さぶし」が平安語で「さびし」になる理由 YUY
第4章 「吾君」が「あぎ」に、「籠(ル コ)モり水」が「コモりづ」になる理由 YMY
§1 「田」は「た」なのに「山田」が「やまだ」と読まれるのはどうしてか
§2 双挟潜化によって「吾君」は「あぎ」に、「いざな君」は「いざなぎ」になる
§3 「籠(ル コ)モり水」が「コモりづ」になる理由
第5章 「十」が「ト乙(6ポ)を」「そ甲(6ポ)」「ト乙(6ポ)」「ソ乙(6ポ)」に変化する理由
§1 「十」が「ト乙(6ポ)を」「そ甲(6ポ)」「ト乙(6ポ)」「ソ乙(6ポ)」に変化する理由
§2 「針」「百合」「しり方」の「り」が東方語で「る」と読まれる理由
第4部 ナ行変格活用と動詞終止形の活用語足
第6章 ナ変動詞・ナ変助動詞の語素構成と動詞終止形の活用語足W
§1 ナ変動詞・ナ変助動詞の活用語胴
§2 近畿語でのナ変連体形の遷移過程
§3 東方語でのナ変連体形の遷移過程
§4 動詞終止形の活用語足はW
§5 ナ変の活用形式付加語素WRW
第5部 上代語動詞「居」の終止形「う」
第7章 上代語動詞「居(ル う)」の終止形が「う」になる理由
§1 上代語動詞「居(ル う)」の終止形・連体形・連用形の用例
§2 上代語「居」終止形の語素構成と遷移過程
第6部 上代語上甲段活用動詞「見」の終止形
第8章 上代語「見」の終止形が「み」になる理由
§1 上代語「見」の終止形が「み」になる理由
§2 終止形が「い甲」段一音節になる活用は上甲段活用
§3 上甲段動詞「見」の語胴形Yます用法
第7部 上二段活用動詞終止形の遷移過程と連体形「居る」「見る」「見る」「過ぐる」「生ふ」の遷移過程
第9章 上代語上二段活用動詞の終止形の遷移過程
§1 呼応潜顕
§2 「月」が「つキ」とも「つく」とも読まれる理由 WY
§3 上代語の上二段終止形「恋ふ」の遷移過程
§4 上二段動詞の語胴形YYぬ用法の遷移過程
第10章 上代語連体形「見る」「居る」「過ぐる」「生ふ」の遷移過程
§1 上代語連体形「見る」の遷移過程
§2 「居」の連体形が上代語で「ゐる」になる遷移過程
§3 近畿語上二段連体形「過ぐる」と東方語上二段連体形「生(ル お)ふ」の遷移過程
第11章 助動詞「らし」「らむ」「∧"し」への接続
§1 助動詞「らし」「らむ」への接続
§2 助動詞「∧"し」への接続
第8部 上乙段活用動詞「干(ル ふ)」「嚔(ル ふ)」「居(ル う)」「廻(ル む)」
第12章 「干(ル ふ)」「嚔(ル ふ)」「居(ル う)」「廻(ル む)」は上乙段活用動詞
§1 未然「ヒ乙(6ポ)」・連用「ヒ乙(6ポ)」・終止「ふ」と活用する動詞「干(ル ふ)」
§2 橋本進吉の“上代語已然形「干(ル ふ)れ」”説
§3 未然形連用形の語尾が「イ乙」段である動詞の終止形語尾は活用行の「う」段になる
§4 連体形が「ミ乙(6ポ)る」、連用形が「ミ乙(6ポ)」の動詞「廻(ル む)」
§5 有坂秀世の“上代語「廻」は上一段”説
§6 上乙段活用動詞「干(ル ふ)」「居(ル う)」「廻(ル む)」
§7 上代語の上甲段活用・上乙段活用は平安語ではすべて上一段活用に変化する 3470
§8 上乙段活用動詞「干」「廻」の終止形・連体形の遷移過程
第二編 四段動詞に続く助動詞「り」と動詞の命令形
第1部 体言を表す動詞連用形と四段動詞に続く助動詞「り」
第13章 体言を表す動詞連用形「行き」「死に」「見」「居(ル ゐ)」「廻(ル ミ)」「恋ヒ」の遷移過程
第14章 四段動詞に助動詞「り」が続く場合の遷移過程 Y+AY
§1 「家」第二音素節が「へ甲(6ポ)」「ひ甲(6ポ)」「は」「∧乙(6ポ)」に変化する理由
§2 四段動詞に助動詞「り」が続く場合の遷移過程
第2部 動詞命令形
第15章 動詞命令形の活用語足はYOY
§1 動詞命令形の活用語足はYOY
§2 上代語の四段・ナ変・上二段の命令形の遷移過程
§3 上代語上甲段命令形の遷移過程
第三編 弱母音素∀(ル ターン エイ)と動詞未然形
第1部 弱母音素∀
第16章 弱母音素 ∀
第2部 動詞未然形の仮定用法・ずむ用法
第17章 動詞未然形の仮定用法・ずむ用法
§1 動詞未然形仮定用法の遷移過程
§2 動詞未然形ずむ用法の遷移過程
第四編 兼音素¥(ル イェン)とサ変・カ変と動詞已然形
第1部 兼音素¥
第18章 兼音素¥
§1 「網」第二音素節の母音部¥は「い甲」を形成する
§2 「寄す」第一音素節¥YO・「帯」第一音素節¥¥O
第2部 否定助動詞「ず・にす」
第19章 否定助動詞「ず・にす」 N¥+SU
§1 否定助動詞「ず・にす」の終止形は「N¥+SU+W」
§2 大野晋のani-su説と私の「∀+N¥+SU+W」説との相違点
§3 否定助動詞連体形「ぬ・の」は「N¥+AU」
§4 平安語・現代語での否定助動詞の終止形・連体形
第3部 「思(ル おモ)ふ」「面(ル おモ)」「持(ル モ)つ」の「モ乙(6ポ)」が駿河で「メ乙(6ポ)」になる理由
第20章 近畿語の「思(ル おモ)ふ」「面(ル おモ)」「持(ル モ)つ」の「モ乙(6ポ)」が駿河の言語で「メ乙(6ポ)」になる理由
第4部 サ行変格活用動詞・カ行変格活用動詞
第21章 サ変動詞「為(ル す)」の活用
第22章 カ変動詞「来」の活用
§1 上代語「来」の活用
§2 平安語命令形「来よ」の遷移過程
第5部 上代語の動詞已然形
第23章 動詞已然形の接続用法と コソや用法
§1 万葉集では「等」「登」は清音を表す仮名
§2 四段動詞已然形語尾の母音部はYO¥
§3 動詞已然形の接続用法と コソや用法
§4 上甲段・上二段の已然形の遷移過程
§5 サ変・カ変の已然形の遷移過程
§6 「人をヨく見(ル み)ば猿にかモ似る」の「見」は已然形
§7 完了助動詞「ぬ」の已然形接続用法「ぬれ」の遷移過程
§8 助動詞「ず・にす」の已然形接続用法「ね」の遷移過程
第五編 兼音素Ω(ル オメガ)と下二段動詞
第1部 兼音素Ω
第24章 兼音素Ω
§1 「わ」にも「あ」にもなる「吾」の父音部はΩ(ル オメガ)
§2 「思(ル おモ)ひ」の第一音素節はΩ
第2部 助動詞「む」
第25章 意志助動詞「む」の助動詞語素はMΩ
§1 意志助動詞終止形・連体形が近畿語で「む」、東方語で「も」になる理由
§2 サ変・カ変に助動詞「む」が続く場合の遷移過程
第26章 平安語「あはん」と現代語「いません」「ましょう」
§1 平安語の撥音便「あはん」の遷移過程
§2 上代語「まさず」と現代語「ません」の遷移過程
§3 平安語ウ音便「ませう」・現代語拗音便「ましょう」の遷移過程
第3部 単音節下二段活用とエ乙型複音節下二段活用
第27章 単音節下二段とエ乙型複音節下二段の遷移過程
§1 単音節下二段動詞と複音節下二段動詞
§2 単音節下二段の遷移過程
§3 エ乙型複音節下二段の遷移過程
第4部 東方語下二段「忘ら」「明け甲(6ポ)ぬ」
第28章 東方語下二段の語尾が「あ」段・「え甲」段にもなる理由 YAY
第5部 可得動詞「焼ケ」「見ゆ」と可得助動詞「ゆ・らゆ・る」
第29章 可得動詞 ―焼ケむ柴垣・見ゆ・引ケ鳥
§1 「焼ケむ柴垣」の「焼ケ」は可得動詞
§2 可得動詞「見ゆ」
§3 可得動詞は動詞の活用語胴に下二段「得(ル う)」が続いたもの
§4 「引ケ去(ル い)なば」の他動詞「引ケ」と「引ケ鳥」「引ケ田」の可得動詞「引ケ」
§5 現代語の可得動詞「見える」「聞ける」の遷移過程
第六編 動詞連用形とラ変動詞
第1部 動詞連用形の体言用法・つてに用法
第30章 動詞連用形体言用法・つてに用法
§1 動詞連用形体言用法
§2 「吹き」に「上ゲ」が続いて「ふきあゲ」になる理由
§3 連用形つてに用法の遷移過程
§4 東方語カ変「来」の連用形が「キ乙(6ポ)」になる理由
§5 否定助動詞「ず」の連用形つてに用法「に」「ず」
第2部 四段動詞の連用形い音便
第31章 四段動詞連用形の促音便・い音便
§1 現代語の促音便「持って」「取って」の遷移過程
§2 動詞連用形が い音便を起こす理由
第3部 ラ行変格活用動詞
第32章 ラ変動詞「有り」の活用
§1 ラ変動詞「有り」
§2 ラ変動詞「をり」
§3 完了存続助動詞「たり」の語素構成
§4 ラ変「あり」の語胴形WWら用法・語胴形WMW∧"し用法
§5 山口佳紀の“「有り」の終止形は上代語より一段階前には「ある」だった”説
第七編 助動詞「す」「ふ」「ゆ・らゆ・る」「なふ」および助詞「う」
第1部 尊敬助動詞「す」・継続助動詞「ふ」・可得助動詞「ゆ・らゆ・る」「る・らる」
第33章 尊敬助動詞「す」・継続助動詞「ふ」 OAYS・OAYP
§1 尊敬助動詞「す」 OAYS
§2 継続助動詞「ふ」 OAYP
第34章 可得助動詞「ゆ・らゆ・る」「る・らる」 OAYRY
§1 上代語の可得助動詞「ゆ・らゆ・る」
§2 平安語の可得助動詞「る・らる」の遷移過程
§3 現代語の可得助動詞「れる」「られる」の遷移過程
第2部 助詞「う」と“時”を表す「う」
第35章 助詞「う」と動詞の語素形う用法 WΩW
§1 近畿語「過ぐす」が東方語で「過ごす」になる理由
§2 助詞「う」および動詞の語素形う用法「行くさ」「来(ル く)さ」
§3 近畿語「来るまで」と東方語「来(ル く)まで」
第36章 “時”を表す「う」と「何時(ル いつ)」「いづれ」の語素構成
§1 “時”を表す「う」
§2 「昼」「夜(ル よる)」の語素構成・遷移過程
§3 “何時”の意味の「いつ」の語素構成・遷移過程
§4 上代語「いづれ」の語素構成・遷移過程と現代語「ドれ」の遷移過
第37章 「射ゆ猪(ル しし)」の語素構成
第3部 東方語否定助動詞「なふ」と東方語「来なに」「付かなな」
第38章 東方語否定助動詞「なふ」 N¥+AOP
第39章 東方語「来なに」「付かなな」
§1 東方語で「な」「の」に変化する助詞「に」の本質音
§2 東方語「来(ル コ)なに」「付かなな」の遷移過程
第八編 動詞・助動詞の語素形Y用法と助動詞「き」「り」「ませ・まし」
第40章 なソ用法での動詞は語素形Y用法
第41章 助動詞「り」がカ変・サ変・上甲段・下二段・上二段の動詞に続く遷移過程
§1 助動詞「り」がカ変・サ変・上甲段・下二段・上二段に続く遷移過程
§2 東方語「勝ちめり」の語素構成・遷移過程
第42章 過去助動詞「き」 SYK
§1 過去助動詞「き」の遷移過程
§2 否定助動詞「ず」に「き」が続く遷移過程
§3 東方語「固メトし」の遷移過程
第43章 反実仮想助動詞「ませ・まし」 MAS
第九編 上代九州語および続日本紀・延喜式以後の日本語
第1部 上代九州語で上代特殊仮名「迷」甲乙両用問題と「いさちる・いさつる」問題を解く
第44章 日本書紀の「迷」は「メ乙(6ポ)」「め甲(6ポ)」両用なのか
§1 日本書紀の「迷」はすべて「メ乙(6ポ)」である
§2 上代九州語「いさちる」
§3 ク活用形容詞「醜(ル しコ)女き」は九州語で「しコメ乙(6ポ)き」
第2部 広瀬本万葉集東歌で“心”が「吉々里(ル ききり)」と読まれる理由
第45章 “心”が広瀬本万葉集東歌で「吉々里(ル ききり)」、古事記で「紀理(ル キり)」、古今集甲斐歌で「けけれ」と読まれる理由
§1 広瀬本万葉集東歌で“心”が「吉々里(ル ききり)」と読まれる理由
§2 「寝床」の「床」が「ド乙(6ポ)コ乙(6ポ)」とも「ど甲(6ポ)」とも読まれる理由
第3部 続日本紀の「賜∧乙(6ポ)る」「荒ビ乙(6ポ)る」と『延喜式』の「荒び甲(6ポ)る」
第46章 上代近畿語の「賜へ甲(6ポ)る」が続日本紀で「賜∧乙(6ポ)る」になるのはどうしてか
§1 続日本紀宣命の「荒ビ乙(6ポ)る」と延喜式祝詞の「荒び甲(6ポ)る」
§2 上代近畿語の「賜へ甲(6ポ)る」が続日本紀で「賜∧乙(6ポ)る」になるのはどうしてか
§3 平安語四段活用・現代語五段活用の命令形
第4部 下二段「消(ル く)」「蹴(ル く)ゑ」の活用の遷移過程
第47章 自動詞「消(ル く)」の活用が上代語ではカ行下二段、平安語ではヤ行下二段に変化する理由
§1 平安語下二段活用の一般的な遷移過程
§2 自動詞「消」が上代語ではカ行下二段、平安語ではヤ行下二段、現代語でア行下一段になる理由
第48章 「蹴(ル く)ゑ」の活用が下二段から下一段・五段へと変化する理由
§1 「蹴ゑ」は上代語ではワ行下二段活用し、平安語前期の辞書類では終止形が「くゑる」「くぇる」「くゆ」「く」になる
§2 平安語の物語で下一段活用する「蹴る」の遷移過程
§3 現代語五段活用「蹴る」の遷移過程
§4 平安語W潜化遷移・現代語W潜化遷移
§5 上二段動詞「ヨロコぶ」が再動詞化して四段動詞「ヨロコぶ」になる経緯
第5部 平安語・現代語の動詞活用
第49章 平安語「見る」「居る」の終止形・連体形・已然形の遷移過程
§1 平安語「見る」の終止形・連体形・已然形の遷移過程
§2 平安語「居る」の終止形・連体形・已然形の遷移過程
第50章 「い甲」「イ乙」の識別が平安語で消滅する理由
§1 平安語上二段活用の遷移過程
§2 平安語上一段活用「嚔る」の終止形・連体形の遷移過程
§3 「い甲」「イ乙」の識別が平安語で消滅する理由
第51章 現代語の動詞活用の遷移過
§1 上一段・サ変・カ変および四段(上代語ではナ変)の終止形の遷移過程
§2 上一段・サ変・カ変の命令形の遷移過程
§3 意志形「行こう」「見よう」「起きよう」「居よう」「しよう」「来よう」「寝よう」の遷移過程
§4 上一段(上代語の上甲段・上二段)と五段(上代語ではナ変)の連体形・仮定形
§5 下一段動詞の終止・連体・仮定・命令の遷移過程
§6 上一段(上代語の上二段)・サ変の未然形の遷移過程
第52章 大野晋の動詞古形説と私の動詞本質音説の相違点・共通点
§1 上代特殊仮名の音素配列についての大野晋説と私見との相違点・共通点
§2 動詞語素についての大野説と私見との相違点
§3 連用形・終止形の活用語足についての大野説と私見との相違点
第十編 助詞「ノ・な」「ロ・ら」「あ」
第1部 助詞「ノ・な」「ロ・ら」「あ」
第53章 助詞「ノ・な」 N∀Ω
§1 助詞「ノ」「な」の意味・用法
§2 助詞「ノ・な」の本質音はN∀Ω
第54章 助詞「ロ・ら」 R∀Ω
第55章 助詞「あ」
§1 複数を表す助詞「あ」
§2 動詞語素に助詞「あ」が付く用法
第2部 「吾が大王」が「わゴおほきみ」に、「吾が思ふ」が「わがモふ」になる理由
第56章 「吾が大王」が「わゴおほきみ」になる理由
§1 「常(ル トコ)」「苑(ル ソノ)」が訓仮名で「ト」「ソ」になる理由
§2 「吾君(ル あぎ)」「いざな君(ル ぎ)」の遷移過程
§3 「大」は「おほ」とも「お」とも読まれる
§4 「吾が大王」が「わゴおほきみ」になる理由
§5 「翁(ル おきな)」「大王(ル おぎ)ロなし」の遷移過程
第57章 「が+思ふ」が「がモふ」になる理由
§1 「吾が家(ル へ)・吾ぎ家」と「吾ぎ妹(ル も)」
§2 「心は思(ル モ)∧ド」「吾が思(ル モ)ふ」「吾が面(ル モ)て」で「お」が脱落する理由
第十一編 形容源詞と形容源化語素
第58章 足跡(ル あト)・下下(ル したた)
§1 船余(ル ふなあま)り・雨籠(ル あまゴ)モり
§2 「足跡」が「あト」、「足結ひ」が「あゆひ」、「鐙(足踏み)」が「あぶみ」と読まれる理由
§3 「下下」が「したた」と読まれる理由
第59章 「荒し男」の「荒し」は形容源詞、「し」は形容源化語素S¥
§1 「荒し男」の「荒し」は形容源詞、「し」は形容源化語素S¥
§2 形容源詞の連体用法
§3 形容源詞は後続語と縮約する場合としない場合がある
§4 形容源詞の已然用法
§5 「苦しみ」に「し」があり、「寒み」に「し」がない理由
§6 「悲しさ」「羨(ル トモ)しさ」に「し」があり、「無さ」「良さ」に「し」がない理由
第十二編 形容詞の語素構成と活用
第1部 形容詞の終止形・連用形・連体形・未然形
第60章 形容詞終止形語尾にカ行音節がない理由
§1 「苦し」終止形が「くるし」に、「寒し」終止形が「さむし」になる理由
§2 現代語終止形で「くるしい」に「し」があり、「さむい」に「し」がない理由
第61章 連用形「悲しく」に「し」があり、連用形「深く」に「し」がない理由 ―シク形容∀群とク形容A群
§1 「悲し」の連用形「かなしく」に「し」がある理由 ―シク形容∀群
§2 「深し」の連用形「ふかく」に「し」がない理由 ―ク形容A群
§3 形容詞連用形にラ変動詞「有り」が下接・熟合したカリ活用形容詞
§4 桜井茂治説と私見との相違点
§5 形容詞連用形が平安語でウ音便、現代語で拗音便・オウ音便を起こす理由
第62章 連体形「苦しき」に「し」があり、連体形「寒き」に「し」がない理由 YΩY
§1 「幸く」が「さきく」「さけく」「さケく」「さく」と読まれる理由
§2 形容詞連体形語尾が「き甲(6ポ)」「け甲(6ポ)」「ケ乙(6ポ)になるのは活用語足がKYΩYだから
§3 連体形「苦しき」に「し」があり、連体形「寒き」に「し」がない理由 ―シク形容W群・ク形容U群
§4 連体形「トモしき」に「し」があり、連体形「広き」に「し」がない理由 ―シク形容Ω群・ク形容O群
§5 現代語形容詞連体形が「くるしい」「さむい」になる理由
§6 ク形容U群「古し」の語素構成
第63章 形容詞未然形の仮定用法・ ずむ用法 ―シク形容W¥Ω群
§1 形容詞未然形仮定用法の用例
§2 形容詞未然形仮定用法の遷移過程
§3 形容詞未然形ずむ用法の遷移過程
第2部 ク活用「しコメき」「武き」とシク活用「うれしく「らしき」
第64章 ク活用「しコメしコメき」「武き」 ―ク形容Y∀Y群
§1 「しコメしコメき」はク形容Y∀Y群
§2 「若たける」「獲加多支鹵(ル わかたきろ)」と「武き」
第65章 ク活用「うれたし」とシク活用「うれし」―シク形容YAYYO群
§1 ク活用「うれたし」は「うRYA+YYTAし」
§2 シク活用「嬉し」は「うRYA+YYOし」
第66章 助動詞「らし」がシク活用になる理由 ―ク形容YA群
第3部 形容詞の已然形
第67章 形容詞已然形語尾が「けれ」「け」「か」「き」になる理由 ―KYAYRY∀YM・KYAYRY∀Yとク形容¥O¥群
§1 形容詞已然形の接続用法・コソや用法
§2 形容詞已然形語尾「けれ」「け」「か」の遷移過程
§3 形容詞已然形語尾「き」の遷移過程
第4部 形容詞きう縮約・否定助動詞ずう縮約
第68章 形容詞くは語法・形容詞くトモ語法
§1 形容詞くは語法の語素構成
§2 形容詞くトモ語法の語素構成
第69章 否定助動詞ずは語法
§1 否定助動詞ずは語法が仮定条件を表す理由
§2 ずは語法ぐらいなら用法・もちろん用法
第十三編 形容詞はどうしてク活用とシク活用に分岐するのか
第1部 穏(ル おだ)ひし・斎斎(ル ゆゆ)し・寂(ル さぶ)し・緩(ル ゆら)し
第70章 形容源詞「おだひし」とシク活用形容詞「さぶし」「斎斎(ル ゆゆ)し」 ―Y群・UY群・YUY群
§1 形容源詞「おだひし」 ―シク形容Y群
§2 シク活用連用形「寂しく」の遷移過程 ―シク形容YUY群
§3 シク活用連体形「斎斎しき」の遷移過程 ―シク形容UY群
第71章 上代語形容源詞「ゆらみ」と平安語ク活用ゆるし」 ―ク形容∀W群
第2部 語幹末尾が「エ乙」段・「え甲」段の形容詞
第72章 「さやケし」の「ケ」と「さやかに」の「か」 ―ク形容¥A¥群
第73章 ク活用する助動詞「∧"し」 ―ク形容YO¥群
第74章 葦原ノしけしき小屋・葦原ノしコ男 ―シク形容¥OY群
第75章 シク活用「異(ル け)し」「うらめし」 ―シク形容¥∀Y群
第76章 ク活用「繁(ル しゲ)し」「まねし」 ―ク形容¥∀¥群
第3部 語幹末尾が「お甲」段・「お丙」段の形容詞
第77章 楽し・か黒し・かしこし ―シク形容ΩWΩ群・ク形容ΩOΩ群・ク形容∀U∀群
§1 楽し ―シク形容ΩWΩ群
§2 か黒し・尊(ル たふと)し・清し ―ク形容ΩOΩ群
§3 ク活用「畏(ル かしこ)し」 ―ク形容∀U∀群
第78章 白し・著(ル しる)し・トほしロし ―ク形容WAW群・ク形容WOW群
§1 白し ―ク形容WAW群
§2 著(ル しる)し・いちしろ甲(6ポ)し ―ク形容WOW群
§3 遠著(ル トほしロ)し
第79章 形容源詞「いそし」と「いと県主」「いト手」 ―シク形容OWO群
第4部 語幹末尾に助詞がある形容詞
第80章 語幹末尾に助詞「あ」が付いているシク活用形容詞「懐かし」「悔やし」 ―シク形容A¥群・シク形容WA¥群
§1 語幹が「四段動詞語素+助詞あ」であるシク活用形容詞「懐かし」 ―シク形容A¥群
§2 上代語「ヨロコぼし」が平安語で「ヨロコばし」に変化する理由
§3 語幹が「下二段動詞語素+助詞あ」であるシク活用形容詞「痩(ル や)さし」
§4 語幹が「上二段動詞語素+助詞あ」であるシク活用形容詞「悔やし」 ―シク形容WA¥群
第81章 語幹末尾に助詞「う」が付いているシク活用形容詞「斎つくし」「思ほしき」 ―シク形容WΩW群
§1 語幹が「動詞語素+助詞う」であるシク活用形容詞「斎つくし」 ―シク形容WΩW群
§2 「思ほしき」「厭ほしみ」「たノモしみ」の語素構成・遷移過程
第82章 語幹末尾に助詞「か」が付いているシク活用「恥づかし」「いぶかし」およびク活用「いぶせし」 ―ク形容YOY群
§1 恥づかし
§2 「いぶせし」は「いぶ+為(ル せ)+し」 ―ク形容YOY群
第83章 「うむがし」の「が」は助詞「が」
第84章 語幹末尾に助詞「ロ・ら」があるシク活用形容詞 ―シク形容∀Ω群
§1 シク活用「良ロし・良らし」
§2 シク活用「賞(ル メ)づらし」
第5部 「またけむ・まソけむ」と「おほし」
第85章 「またけむ・まソけむ」と「おほし」 ―ク形容Ω∀群・ΩΩ群
§1 「全けむ」が「またけむ」にも「まソけむ」にもなる理由 ―ク形容Ω∀群
§2 「全く」が現代語で促音便「まったく」になる理由
§3 形容詞「おほし」がク活用する理由 ―ク形容ΩΩ群
第6部 補助動詞「なす」「ノす」と形容詞語幹末尾の「如(ル な)」
第86章 補助動詞「なす・ノす」
第87章 「如(ル な)=NOA」が語幹末尾にある形容詞 ―ク形容OA群
§1 をぢなし
§2 つたなし
§3 いらなし
§4 すくなし
§5 きたなし
§6 すかなし
§7 おぎロなし
第88章 「たづ」の原義とシク活用「たづたづし」 ―WΩW
§1 鶴(ル つる)が「たづ」と呼ばれる理由
§2 シク活用「たづたづし」
第89章 「おほほし・おぼほし」「おほロか」「おほならば」
§1 おほほし・おぼほし
§2 「おほ=ΩMPΩ」の原義と「おほほし・おぼほし」の意味
§3 おほロか・おほならば・己が生(ル を)をおほにな思ひソ・朝霧ノおほ
第90章 語幹末尾に「助詞か+如(ル な)」があるク活用形容詞
§1 たづかなし
§2 おほつかなし
第7部 「欲(ル ほ)し」「時じ」「同じ」
第91章 動詞「欲(ル ほ)る」と形容詞「欲(ル ほ)し」 ―シク形容¥群
§1 四段動詞「欲(ル ほ)る」 POR¥
§2 サ変動詞「欲りす」
§3 「見が欲(ル ほ)し国」の「欲し」は形容源詞
§4 形容詞「欲(ル ほ)し」
第92章 シク活用形容詞「時じ」と形容源詞「鳥じ」
§1 シク活用形容詞「時じ」
§2 形容源詞「鳥じモノ」
第93章 語幹末尾に「無(ル な)」がある形容詞
§1 心無し・あづき無し
§2 かたじケ無し
第94章 形容源詞「おなじ・おやじ」とシク活用形容詞連体形「おなじき」
§1 形容源詞「おなじ・おやじ」
§2 シク活用形容詞連体形「おなじき」の遷移過程
第8部 否定推量助動詞助動詞「ましじ」「じ」
第95章 上代語「ましじ」・平安語「まじ」
第96章 否定推量助動詞「じ」
第9部 形容素詞の連体用法・已然用法
第97章 東方語「あやはとモ」は形容素詞の已然用法 ―ク形容AU群
§1 「あやふかる」「あやほかト」「あやはとモ」の第三音素節はPAU
§2 形容素詞の連体用法
§3 東方語「あやはとモ」の「あやは」は形容素詞の已然用法
§4 形容詞「あやふかる」「あやほかト」と形容素詞「あやはとモ」の遷移過程
第10部 ク・シクが分岐するのはどうしてか
第98章 ク・シク分岐語幹末母音部説
§1 “ク活用形容詞は状態を表し、シク活用は情意を表す”説には例外が多い
§2 語幹末尾の母音部の音素配列によってク活用・シク活用の区別が定まる
第十四編 ク語法は「連体形+AYく」
第99章 ク語法「AYく」説
§1 大野晋のク語法aku説
§2 ク語法「AYく」説
§3 形容詞ク語法の遷移過程 ―近畿語「悲しけく」「無けく」と東方語「しげかく」
§4 動詞のク語法の遷移過程
§5 完了助動詞「ぬ」・否定助動詞「ず」のク語法の遷移過程
§6 詠嘆助動詞「け甲(6ポ)り・ケ乙(6ポ)り・かり」と過去推量助動詞「けらし」
§7 過去助動詞「き」のク語法が「けく」にも「しく」にもなる理由
参考文献
おわりに