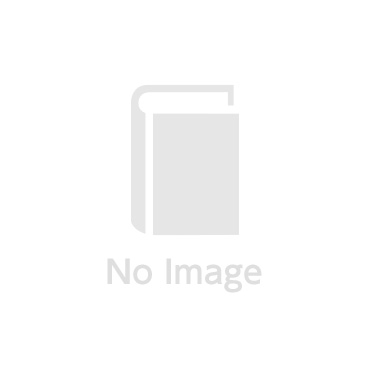緒 言
A 樫山村 地名考および「御水帳」分析による歴史と変遷
はじめに
第一章 樫山村地名考―慶長、寛文、明治、平成の地名比較
(『高根町地名誌』1990:文責 大柴宏之・谷口彰男、引用参考)
一節 検地帳に在る字、明治期における役場登録の字
1.慶長7年(1602)『甲州逸見筋樫山村御水帳』に在る字
2.寛文6年(1666)『甲州逸見筋樫山村検地御水帳』に在る字
3.明治8年編纂 役場に登録された小字と地番
二節 樫山村―明治、平成、慶長、寛文、地名比較一覧
1.樫山村―1(大門川東岸地区)
2.樫山村―2(大門川西岸地区)
A―地図1.樫山村-1.(大門川東岸地区)
A―地図2.樫山村-2.(大門川西岸地区)
第二章 『御水帳』解読分析―樫山村 慶長および寛文
一節 慶長7年(1602)『甲州逸見筋樫山村御水帳』解読分析
1.樫山村慶長7年 字・筆数・その他一覧
2.樫山村慶長7年 田、畑合計
3.樫山村慶長7年 屋敷数・名請人・規模・分布
二節 寛文6年(1666)『甲州逸見筋樫山村御検地御水帳』解読分析
1.樫山村寛文6年 字・筆数・その他一覧
2.樫山村寛文6年 田、畑、屋敷合計
3.樫山村寛文6年 屋敷数・名請人・規模・分布
三節 樫山村 『御水帳』慶長7年と寛文6年の田畑・屋敷比較
1.樫山村 慶長・寛文 田、畑、字数、筆数、石高比較
2.樫山村 慶長・寛文 屋敷数、規模分布比較
3.まとめ
第三章 地名考および「御水帳」から見える樫山村の歴史
一節 慶長から寛文 字数、筆数、石高および東・西地区
1.字数3.6倍・筆数2.2倍、石高約2倍の増加、耕地の生産力は低い
2.大門川を挟み東・西地区の字数と筆数の割合は約7対3
二節 慶長、寛文、平成の変遷
1.慶長から寛文に消滅または減少著しい字および舟ガ川流域
2.慶長から寛文、平成の現在に存続している字
3.慶長・寛文に無く、平成の現在に在る字
4.居村の変遷-当初の居村(集落)から西村、東村、上村の順に誕生
5.慶長・寛文時において「村」は東に在り西には無い
6.慶長から寛文、そして平成の変遷の中で注目の字
1)「馬捨場」 2)「八ヶ岳権現」「風切り」 3)寛文時、川俣川沿いの字の殆どが長沢村入作
4)「御水神」の消滅 5)弘化2年当時「弘法水、弘法坂」は無かった
6)寛文検地に在る「番屋」 7)「まつはのそり」「おたまいし・お玉石窪」
7.慶長時から寛文時に増大する平沢村、長沢村、浅川村からの入作
三節 慶長、寛文において筆数の多い字の変遷から見えること
1.樫山村東地区:舟ガ川流域の字・筆数変動と新開拓地
2.樫山村西地区:深沢川流域等の著しい開発
おわりに
注
Aー写真1.慶長七年「甲州逸見筋樫山村御水帳」表紙
Aー写真2.寛文六年「甲州逸見筋樫山村御検地水帳」表紙
Aー絵図1.「天保八年酉年八月 樫山村高家数人数並居村耕地など巡見様に差上の絵図」(控)
Aー絵図2.「樫山村神明社々領絵図」(控 年不詳)
Aー絵図3.「樫山村つきの木坂外田方絵図」(控 弘化二年三月廿日)
B 浅川村 地名考および「御水帳」分析による歴史と変遷
はじめに
第一章 浅川村地名考―慶長、寛文、明治、平成の地名比較
(『高根町地名誌』1990:文責 大柴宏之・谷口彰男、引用参考)
一節 検地帳に在る字、明治期における役場登録の字
1.慶長7年(1602) 『甲州逸見筋樫山之内浅川村御水帳』に在る字
2.寛文6年1666)『甲州逸見筋浅川村御検地水帳』に在る字
3.明治8年編纂 役場に登録された小字と地番
二節 浅川村―明治、平成、慶長、寛文の地名比較一覧
B―地図1.浅川村
第二章 『御水帳』解読分析―浅川村 慶長および寛文
一節 慶長7年(1602)『甲州逸見筋樫山村の内浅川村御水帳』解読分析
1.浅川村慶長7年 字・筆数・その他一覧
2.浅川村慶長7年 田、畑合計
3.浅川村慶長7年 屋敷数・名請人・規模・分布
二節 寛文6年(1666)『甲州逸見筋浅川村御検地水帳』解読分析
1.浅川村寛文6年 字・筆数、その他一覧
2.浅川村寛文6年 田、畑、屋敷合計
3.浅川村寛文6年 屋敷数・名請人・規模・分布
三節 浅川村『御水帳』慶長7年と寛文6年の田・畑・屋敷比較
1.浅川村 慶長・寛文 田、畑、字数、筆数、石高比較
2.浅川村 慶長・寛文 屋敷数、規模分布比較
3.まとめ
第三章 地名考および「御水帳」から見える浅川村の歴史
一節 慶長から寛文 字数、筆数、石高および東・西地区
1.字数4.9倍・筆数2倍以上・石高2.3倍の増加、耕地の生産力は最低
2.大門川を挟み東・西地区の字数と筆数の割合は約3対7
3.東の耕地限界と西への進出、石高の顕著な増加の背景
二節 慶長、寛文、平成の変遷
1.慶長から寛文時(1602~1666年の間)東に産土神建立により浅川村確立か
2.慶長から寛文に消滅した字「家の前」は、慶長以前の居村か
3.慶長から寛文、平成の現在に存続している字
4.慶長・寛文に無く、平成の現在に在る字―寛文時以降、西の開発は止む
5.慶長から寛文における西(深沢、中沢、西窪)の著しい開発
6.慶長から寛文、そして平成の変遷の中で注目される字
1)「御玉石」「玉野権現」 2)「関所跡」と「関所」 3)「道通」
7.他村から寛文に増大する入作と圧倒的な平沢村入作
三節 慶長、寛文において筆数の多い字の変遷から見えること
1.浅川村東地区:寛文時最多筆数「五郎屋敷」出現と伝承
2.浅川村西地区:深沢川流域の字・筆数増大、新開拓地
おわりに
注
Bー写真1.慶長七年『甲州逸見筋樫山村之内浅川村御水帳』表紙
Bー写真2.寛文六年『甲州逸見筋浅川村御検地水帳』表紙
Bー絵図1.浅川村および樫山村の位置略図
C 近世の樫山村・浅川村
はじめに
第一章 慶長、寛文時の著しい石高増加と住民離散・移動の考察
一節 最低の土地生産力の地において顕著な石高増加
二節 慶長から寛文時 浅川村東の耕地限界と西への進出・開拓
―想定される浅川・長沢・樫山への人口流入と石高増加
三節 離散・移動伝承と浅川
四節 浅川住民の離散・移動―慶長以前にも在ったか
第二章 「玉野権現」浅川村産土神誕生および集落・郷・「村」
一節 慶長から寛文時の「お玉石」「玉野権現」と浅川村・樫山村
二節 「玉川神社造営」と「五郎屋敷」伝承
―「五郎屋敷」は慶長・寛文時の人口流入に因るものだったか
三節 度々「お玉石」移動、「たまの庄」伝承
四節 慶長六年『逸見筋樫山之内浅川村御水帳』とは
―近世の「郷」「村」から
第三章 慶長から寛文 樫山村と浅川村における入作の実態
一節 「入作」定義、前置き、歴史概要
二節 樫山村における字・筆数から見た入作の実態
1.樫山村慶長時(1602年)の入作
2.樫山村寛文時(1666年)の入作
3.樫山村 慶長から寛文の入作
三節 浅川村における字・筆数から見た入作の実態
1.浅川村慶長時(1602年)の入作
2.浅川村寛文時(1666年)の入作
3.浅川村 慶長から寛文の入作
4.まとめ
第四章 「寺社関係」「特別名請人」から見える歴史
一節 樫山村と浅川村 慶長・寛文検地における「寺社関係」「特別名請人」
二節 樫山村の「寺社関係」「特別名請人」および考察
1.山王-樫山村の山王権現(氏神)は「何某」一族から始まった
2.善福寺の歴史と変遷-観音、地蔵信仰
3.大楽院-大楽院は修験院、修験不動寺は後に観音堂となる
4.ひじり-寛文に登場する大楽院とひじり
5.「おし」
6.「牢人」
7.「つかもの」道永・道半・道円
8.海岸寺-樫山村は慶長時1筆、浅川村は慶長・寛文合わせて6筆あり
9.樫山村「寺社関係」と所領地および変遷
三節 浅川村の「寺社関係」「特別名請人」および考察
1.海岸寺
2.常蔵院(法成院、宝城院)
3.正光寺
4.日光院
5.浅川村「寺社関係」と所領地および変遷
おわりに
注
Cー写真1.玉川神社
Cー写真2.玉川神社 奥宮
Cー写真3.お玉石
Cー写真4.浅川村慶長検地帳(1602年)「玉野権現」(初出)
Cー写真5.慶長検地帳(1602年)「入作」の名請人に村の記載なし
Cー写真6.観音堂石段脇に在った修験の石碑および観音堂イ ロ ハ ニ ホ
Cー絵図1.樫山村と浅川村の位置
Cー絵図2.樫山村と浅川村の略図
Cー絵図3.「浅川村字名割付絵之図」(明治初年の浅川村文書から)
D(資料)『貞享三寅年 き里志たん穿鑿?樫山村』解読分析
はじめに(資料入手、「宗門帳」の概要と整理方法、Dの構成)
1.戸および構成内容一覧
2.添家-数、男女別年齢構成
3.人口-全戸の男女別人口、年齢構成
4.縁付き-年齢、縁付先、養子移籍先
5.女房-年齢、婚入元出身村
6.奉公、下人、下女-男女別年齢、年季、奉公先
結 語
文 献