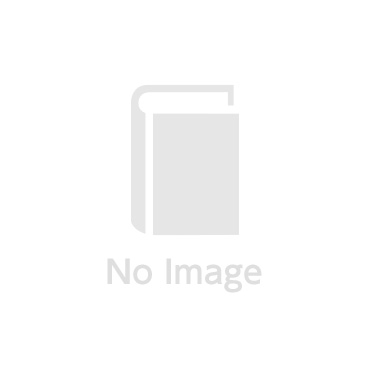第一部 外交実務と国際法
1 日本外交と法の支配
一 「開国」による国際法との出会い
二 戦後処理をめぐって
三 日本と国際裁判
四 国際裁判所の管轄権
五 国際裁判の「積極的」な活用
六 国際刑事裁判所(ICC)への加盟
七 日本の開発途上国に対する法制度整備支援
八 「法の支配」は単なる理念を超えられるか
2 外交実務で「国際法を使う」ということ
一 はじめに
二 国際法に係る意思決定と外交実務
三 国際法に従った外交政策の実施
四 国際法における「ルール造り」と国際約束締結事務
五 むすびに代えて
■国会承認条約 ■行政取極
第二部 国際法の実践
Ⅰ 海洋と管轄権
3 公海漁業の規制と国家管轄権
一 公海自由の原則と旗国主義
二 公海漁業の規制と旗国主義の段階的変容
三 いわゆる「国連公海漁業協定」と国家管轄権
四 公海漁業の規制と国内法
Ⅱ 戦後処理
4 国際法の履行確保と国内裁判所による国際法の適用――いわゆる「米国POW訴訟」をめぐって――
一 国際社会における法の支配の強化に向けて
二 「米国POW訴訟」と日本の戦後処理
三 サンフランシスコ平和条約の戦争請求権関連条項の規範的意義
四 むすびに代えて
Ⅲ 国際刑事裁判所
5 国際刑事裁判所ローマ規程検討会議と侵略犯罪
一 はじめに
二 国際刑事裁判所ローマ規程と日本
三 日本にとってのローマ規程検討会議の特別の意味
四 条約改正の法的整合性――条約法上の若干の考察――
五 むすびに代えて
Ⅳ 紛争の平和的解決
6 紛争処理と外交実務
一 はじめに――外交実務で「国際法を使う」ということ――
二 国際紛争の平和的解決を目指して
三 「国際裁判等」の活用と「紛争処理の強制性」
四 日本と「国際裁判等」
五 むすびに代えて
7 GATTの紛争処理手続と「一方的措置」
一 はしがき
二 条約としてのGATTと「一方的措置」
三 国家責任論から見た「一方的措置」
四 あとがき
第三部 そ の 他
Ⅰ 地域情勢
8 欧州統合の進展と日本〔講演〕
一 はじめに
二 滔々たる欧州拡大の潮流
三 欧州統合の深化をめぐって
四 ユーロの登場
五 欧州統合は非経済の分野まで進んでいる――大きな試練に直面したCFSP――
六 欧州憲法条約草案をめぐる動き
七 外務省欧州局の改組について――欧州全体への政策を考える「政策課」を新設――
9 「中央アジア+日本」対中央アジア政策の新展開
一 中央アジアとは
二 「対シルクロード地域外交」を原点に
三 9・11と戦略環境の変化
四 新たな政策の展開
五 「地域内協力」への支援の蓄積
六 日・西バルカン協力
七 「『眼力』のある外相訪問だった」
■フランス共和国レジオン・ドヌール勲章コマンドゥールを拝叙して ■父の国・母の国
Ⅱ 人 材 育 成
10 日本のリーダーが語る世界競争力のある人材とは―豊かな教養とパブリックの精神を身につけた先駆的なリーダーを目指してほしい
〔対談〕小松一郎 vs 山内進
一 マキャベリズムか至誠で迫るか――外交の本質は?――
二 公務員でなくとも頭の片隅にパブリックを
三 歴史の節目に直接かかわれる醍醐味
四 PKO法が日の目を見定着してきた
五 自由・民主主義・市場経済などの普遍的価値を重視する「価値の外交」
六 もっと日本という国に自信を持ってほしい
11 外務省での仕事を振り返って
一 「進路」を決めるということ
二 職業って何だろう
三 いつ、どうして外務省に入ろうと思ったのか
四 外務省で仕事をして良かったと思うこと
参考資料(逆丁)
[1] 国際海洋裁判所弁論
THE “HOUSHINMARU\\\\\\