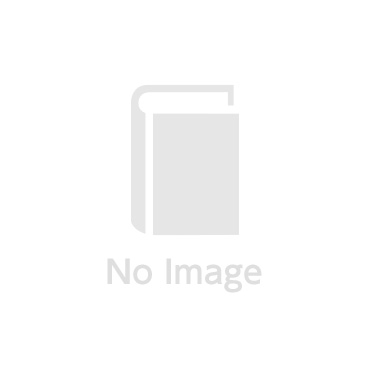★目次
☆第1部 付属基板のこと
◎周波数分解能28ビット!夢の高性能発振器を手に入れたなら
○第1章 DDS付属基板でできること
DDSとは…周波数や波形を作り出す回路
本書のDDS付属基板でできること
ディジタル周波数シンセサイザDDSはここがいい!
Column 拡張基板の頒布のご案内
Column プロにしかできなかったことがいとも簡単に!
Column コピー&ペーストですぐできる!パターン・ライブラリ「パネルdeボード」19
付属CD-ROMのコンテンツと注意事項
◎DDS付属基板の仕様とハードウェアの詳細
○第2章 ディジタル周波数シンセサイザを設計する
DDS付属基板の構成とAD9834
AD9834の周辺回路
出力信号レベル
フィルタの仕様を決める
出力アンプ
75MHz基準クロック発振器
PICマイコンでUSB通信とAD9834のコントロールを行う
電源
プリント基板の仕様
◎パソコンにつないで信号を出してみる
○第3章 DDS付属基板を動かす
手順
◎使いやすい信号発生モジュールに変身!
○Appendix 1 DDS付属基板を仕上げる
準備
仕上げの手順
☆第2部 ディジタル周波数シンセサイザの基礎知識
◎ほかの信号生成方法との違いや信号生成の原理
○第4章 ディジタル制御波形生成IC DDSのハードウェアと動作原理
DDSの基本構成と動作原理
DDSの各ブロックの動作
フィルタ回路
クロック信号源
Column 方形波信号を出すには
◎受信機/測定器/変調器/信号源…周波数が安定しているってすごい!
○第5章 ディジタル周波数シンセサイザDDSの応用
(1)任意周波数の正弦波発生器
(2)可変周波数のディジタル・クロック
(3)SSB受信機の感度レベルの測定
(4)アマチュア無線機のVFO(Variable Frequency Oscillator)代わり
(5)超音波装置の信号源
(6)増幅器の非直線性測定
(7)スカラ・ネットワーク・アナライザ
(8)電源回路の出力インピーダンスの測定
(9)容量/インダクタンス/共振周波数の測定
(10)多相出力の信号源
(11)AM(ASK),FSK,PSK変調信号派の生成
(12)PLLのリファレンス信号源
◎GHz出力型からインピーダンス計測用まで
○第6章 ディジタル周波数シンセサイザのいろいろ
DDSを信号源にしたインピーダンス計測用複合機能IC AD5933/34
高速DDS IC AD9858/AD9859/AD9912/AD9913
直交ディジタル変調機能付き高速DDS AD9957
2.4GHzで動くDDS付き超高速DAC AD9789
任意波形発生器として利用できるDDS AD9834
同期クロックを作り出せるディジタルPLL AD9547
4~20mA電流ループ伝送上で通信を実現するHARTモデム
FPGAで作るDDS
Column DDS基板企画の始まりは一杯飲み屋で…
☆第3部 DDS付属基板をより詳しく知りたい人へ
◎発振器の一番重要な「位相雑音」や波形をチェック
○第7章 DDS付属基板の実力
DDS付属基板に搭載されたDDS IC
DDS付属基板の出力信号のスペクトラムを見る
出力信号のレベル
位相雑音
方形波出力波形をチェック
Column DDS内のD-Aコンバータの出力特性を測定する方法
Column 低周波側の特性を伸ばす改造
◎測定器自身の雑音をキャンセルしてfsオーダのジッタも図る
○Appendix 2 小さな位相雑音も測定できる専用アナライザE5052B
◎内部回路の詳細からレジスタの設計方法まで
○第8章 付属基板に搭載された定番DDS IC AD9834の使い方
AD9834の内部構成と端子の機能
DDS ICのアナログ信号生成のメカニズム
AD9834に見るDDS ICのもう一つの特徴「位相制御」
レジスタを設定してから波形が出力されるまでの遅れ
AD9834のレジスタへの書き込み
Column PLLとDDSを比べてみる
Column AD9834一つで位相の違う2信号を生成する実験
Column がんばれば1GHzの高速アナログ回路は手作りできる
◎パソコンとのインターフェースとDDSのコントロール
○第9章 USBマイコンPIC18F14K50のファームウェア
USBマイコンPIC18F14K50
PICマイコンの開発環境
DDSのレジスタとコントロールの手順
拡張基板をコントロールするファームウェア
Column Microchip-application librariesはアップデートされると互換性がなくなる
Column あれ?PICマイコンとPICkit3がつながらない!?
Column 統合開発環境以外のエディタを使用する場合の注意
◎回路や部品の周波数特性がわかるスカラ・ネットワーク・アナライザに挑戦
○第10章 Excelで作る自動制御PCアプリケーション
テキスト・データで通信してDDS学習キットを操作する
DDS学習キットの操作方法
手作りしたクリスタル・フィルタの周波数の周波数特性を測ってみる
Excelを使って自動測定
Column ハイパーターミナルではなくTeraTermを使うこと
◎電源電圧変動除去比やノイズ性能がUP!シーケンス制御にも対応!
○第11章 多機能化,高性能化するLDOリニア・レギュレータ
アナログ回路には入力電圧変動やノイズの除去能力が高い電源ICがいい
低ノイズ・タイプのLDOを使うメリット
低入力電圧でも動作するリニア・レギュレータのメリット
起動時の突入電流を小さく抑えるソフトスタート機能
立ち上げ順序をマイコンで制御できるパワーグッド機能
主電源に続けて電源を順序良く立ち上げる機能 トラッキング
複数の電源の立ち下げシーケンスを設定できる機能 プログラマブル高精度EN/UVLO
出力コンデンサを強制的に放電して逆流を防ぐ機能 出力ディスチャージ
◎DDSの心臓部!正確かつ安定な出力信号の源
○第12章 付属基板の発信源「水晶発振器」の性能と使い方
DDSには水晶発振器が最適
種類と用途
性能
使い方の基本
内部回路と構造
水晶発振器を使用する際のトラブル
◎DDSの出力をそのまま入力するとアンプやミキサが飽和してしまう…そんなときは
○第13章 ステップ1.5dB,最大減衰量94.5dB,30MHz広帯域アッテネータの設計
アッテネータの必要性
仕様
48dB固定アッテネータ回路
SN比とノイズ・フロア
基板設計
製作した基板の減衰特性
そのほかの機能
◎DDS付属基板でdB表示の周波数特性測定器を作るために
○第14章 周波数特性を測定するログ・アンプの設計
周波数特性測定器を作る
全体構成と動作
変換性能
◎DDS基板やアッテネータ基板を搭載して測定器を作れる
○第15章 液晶ディスプレイ付きベース基板
回路構成