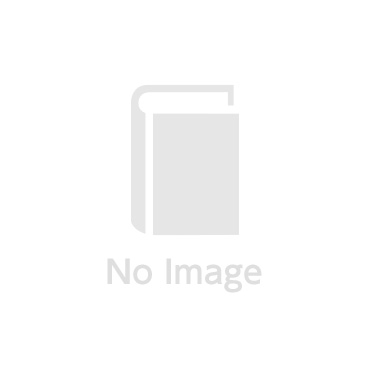はじめに
第一章 フェルメールが生きた時代、オランダそして日本
誰も語らなかったフェルメールと日本/フェルメールの時代のオランダ/フェルメールの時代の日本/デルフトの街と父親の仕事/二十一歳にして親方画家となる非凡な才能/富裕だったフェルメール/オランダの繁栄を保証したユダヤ人/デルフトのユダヤ人/フェルメールの時代の翳り/フェルメールの死/独特だからこそ忘れ去られた画家/フェルメールの「再発見」とジャポニズム/フェルメールの価値を見出すということ
第二章 神の光と自然の光、フェルメールとスピノザの交流
「夜の光」と「昼の光」/フェルメールの「光」とは何か/日本人が『デルフトの眺望』を好む理由/プルーストと『デルフトの眺望』/フェルメールと、日本人の「あるがままの姿」/フェルメールの新しさとは/自然を重視した哲学者スピノザ/フェルメールとスピノザの出会い/『天文学者』と『地理学者』のモデルはスピノザ/徳川家がオランダにもたらした衣服「ヤポンセ・ロック」/フェルメールと光学/スピノザの自然と神無き光/フェルメールと小津安二郎/レンズを通して見ることによる新発見/東洋から来た「バロック」
第三章 『天文学者』と『地理学者』の世界
フェルメールの主題は「現代」/天文学者との交流/キリスト教徒が存在しない日本/十七世紀オランダが育んだ近代の実存性/文化圏の異なる女性たちの図/代表作『アトリエ―絵画芸術』と/『真珠の首飾りの女』も日本の着物を着ていた/全作品の三分の一近くに登場する東洋風の絨毯/手紙が登場する絵画の見方/陶磁器が登場する絵画の見方/オランダの中国磁器輸入を支えた日本の銀/地図が登場する海外の見方/フェルメールのイコノロジー/新しい時代の始まり
第四章 フェルメールのフォルモロジー研究
フェルメールの絵はやはり物語を持っている
◇フォルモロジー1「真珠」 真珠を身につける素直な喜び/真珠を贈り物にできる男性/背景にある最後の審判/普遍的な人間の世界/描かれるものの意味
◇フォルモロジー2「不在の椅子」 不在の椅子/日常生活を描くという変化/フェルメールのフォルム/日本人の顔
◇フォルモロジー3「陶磁器」 西欧の画家が出会った新しい対象/陶磁器と東洋
◇フォルモロジー4「楽器」 楽器、音楽の意味
◇フォルモロジー5「娼婦」 男女関係の表現の基本
◇フォルモロジー6「テーブルの上の絨毯」 「眠る」女ではない『眠る女』/表現力の奥深さ/テーブルの上に置かれる絨毯
◇フォルモロジー7「果物皿」 絵画における心理劇
◇フォルモロジー8「帽子」 笑いと喜びの表現
◇フォルモロジー9「カーテン」 カーテン状の仕切りの表現/非日常的な世界としての絨毯
◇フォルモロジー10「地図」 外界との関係を物語る舞台装置/東洋貿易と地図/意味を持つ静物/フェルメールの観察力
◇フォルモロジー11「画中画」 画中画の現代性
◇フォルモロジー12「キューピッド」 キューピッドと娼婦/風俗画とは異なる表現力/下品にならない理由/道具立てをどう解釈するか
第五章 オランダとフェルメール
宗教に寛容な国オランダ/オランダのユダヤ世界/室内風景の注文/『デルフトの眺望』に描かれているもの