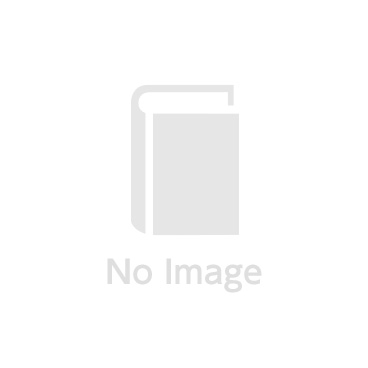埼玉の妖怪
著:大明 敦
絵:池原昭治
内容紹介
みなさんは妖怪に出会ったことはありますか。科学的には妖怪は否定されていますが、私が四歳の頃、麻疹に罹って家で寝ていた時、部屋の襖が開いていて、薄暗い廊下に白い着物を着た小さな子どものようなものが、ふわふわと踊っているように見えたのです。あれは祖母も見たという「ワラシコ」だったのか・・・(はじめにより)
日本人の暮らしや文化、信仰から生まれた妖怪たち。千話を超える伝承から、怖ろしくも心惹かれる謎の世界をめぐる。
第一部 妖怪をめぐって
日本人の暮らしや文化、信仰から生まれた妖怪たち。歴史を紐解き、誕生から現在、そしてこれからの妖怪を考える。
【妖怪とは何か】妖怪という言葉/古典の中の妖怪/妖怪研究の発展/ 水木しげると妖怪/妖怪の現在
【埼玉の妖怪を考える】妖怪のリアリティ/妖怪の名前/不思議な現象を説明するための妖怪/抑止力としての妖怪/地域と生きる妖怪
第二部 妖怪ゆかりの地を訪ねる
妖怪の痕跡が残る場所をめぐり、時空を超えて妖怪との出会いを楽しむ。狐につままれる体験ができるかも。
①氷川女體神社/②第六天神社/③足立ヶ原の黒塚/④寶幢寺/⑤持明院と曼荼羅淵/⑥川越城周辺/⑦小畔川流域/⑧日和田山/⑨鬼鎮神社/⑩少林寺/⑪空滝/⑫矢納の天狗岩
第三部 埼玉の妖怪百態
どの場所に、どのように出現したのか、心優しい妖怪から人を食う妖怪まで、妖怪ごとに伝承をまとめた。身近に棲んでいた妖怪たちの出没記。
【水辺・水中の妖怪】【山や森の妖怪】【路傍・路上の妖怪】【人里の妖怪】【生物・器物などの怪異】
目次
はじめに
第一部 妖怪をめぐって
一 妖怪とは何か
㈠ 「妖怪」という言葉
㈡ 古典の中の妖怪 奈良時代/平安時代/鎌倉・室町時代/江戸時代
㈢ 妖怪研究の発展
㈣ 水木しげると妖怪
㈤ 妖怪の現在 妖怪をめぐる状況の変化/メディアと妖怪/再び脚光を浴びる妖怪/妖怪への期待
二 埼玉の妖怪を考える 妖怪のリアリティ/妖怪の名前/不思議な現象を説明するための妖怪/抑止力としての妖怪/祭りと妖怪/地域と生きる妖怪
第二部 妖怪ゆかりの地を訪ねる
①氷川女體神社/②第六天神社/③足立ヶ原の黒塚/④寶幢寺/⑤持明院と曼荼羅淵/⑥川越城周辺/⑦小畔川流域/⑧日和田山/⑨鬼鎮神社/⑩少林寺/⑪空滝/⑫矢納の天狗岩
第三部 埼玉の妖怪百態
一 水辺・水中の妖怪
河童㈠名前を持った河童/河童㈡河童の詫証文/河童㈢河童のお礼/河童㈣河童の習性/小豆婆/川天狗/おいてけ堀/沢女/竜㈠見沼の竜神/竜㈡左甚五郎の竜/竜㈢龍隠寺の竜と龍泉寺の竜/竜㈣穴沢の竜神/大蛇㈠かしらなしと小次郎/大蛇㈡見沼の大蛇/緋鯉/ヤナ
二 山や森の妖怪
天狗㈠天狗の悪戯/天狗㈡火伏せの天狗/天狗㈢天狗の神通力/天狗㈣天狗隠し/山姥/山姫/山男/テンムサ/ドウマンマナコ/ダイダラボッチ
三 路傍・路上の妖怪
見越し入道/袖引き小僧/ブッツァロベエ/オブゴ/チトリ/カマイタチ/薬缶ころがし/徳利坂/笊坂/フウナデ/笹熊/隠れ座頭/モウ・ゴーヘー/大入道/青坊主/一つ目小僧・一つ目入道/大蓮寺火
四 人里の妖怪
黒塚の鬼婆/鷹橋の鬼女/鬼/夜道怪/オクポ/ボーコー/ネロハ/人喰い仁王・人喰い阿弥陀/八百比丘尼/雪女郎・雪娘/隠し婆/血塊/幽霊/人塊
五 生物・器物などの怪異
偽汽車/猫/送り狼/狐火/獺/蜘蛛/樹木/人形/雷獣/三本足の烏/オーサキ/ネブッチョウ
コラム
鬼退治の英雄・渡辺綱/江戸時代の文献にみえる埼玉の妖怪/埼玉の妖怪研究は川越から始まった?/化け物を鎮めた光千坊様
ISBN:9784878914881
。出版社:さきたま出版会
。判型:A5
。ページ数:256ページ
。定価:2000円(本体)
。発行年月日:2023年06月
。発売日:2023年05月30日
。国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:JBCC。