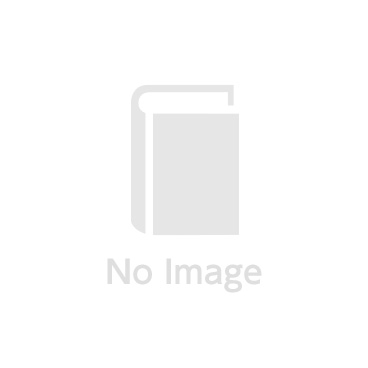学術選書 134
近代民事訴訟法史・オーストリア
著:鈴木 正裕
内容紹介
「わが国の民訴法は、ドイツ法系に属する。本書では、ドイツ法系の民訴法史に大きな痕跡を残したオーストリアの2つの民訴法典をとり上げよう。その一つは、1781年の一般裁判法である。女帝として有名なマリア・テレジアとその長子ヨーゼフ2世の統治時代の産物である。2つめは、1895年の民訴法典である。ドイツ法系民訴法史に残した痕跡ではこのほうが1つめよりよほど巨大である。」
目次
第一部 一七八一年の一般裁判所法――啓蒙主義と民訴法――
一 マリア・テレジアとフリードリヒ大王
(1) 国事詔書/(2) 第一次シュレージェン戦争/(3) 第二次シュレージェン戦争/(4) 七年戦争
二 オーストリア世襲領とベーメン地方
(1) オーストリア世襲領/(2) ベーメン地方
三 マリア・テレジアの内治改革
(1) 前期と後期/(2) 中央官庁群/(3) 最高司法庁の創設/(4) 国事顧問会
四 法令の統一――編纂委員会――
(1) ーメン地方の動き/(2) 編纂委員会/(3) ブリュンの委員会/(4) ヴィーンの委員会/
(5) 訴訟法への特化/(6) 報告委員の交替/(7) 印刷の裁許なし(!?)/(8) 審議の継続
五 AGOの実現――ヨーゼフ二世――
(1) ヨーゼフ二世の啓蒙政策/(2) AGOの公布と施行/(3) 等族と証人宣誓/(4) 三審制と国王裁判所/
(5) 施行の延期/(6) ヨーゼフ二世の死去と諸政策の行方
六 AGOの諸制度
(1) 書面審理主義/(2) 証拠判決/(3) 文書目録作成手続/(4) 弁論の更新の禁止――同時提出主義――/
(5) 裁判官と弁護士
七 AGOとCJF
(1) プロイセンのCJF/(2) AGOとCJF
八 AGOの修正――西ガリチン法――
(1) 西ガリチン法の成立/(2) 西ガリチン法の施行地域
第二部 一八九五年の民訴法――社会政策と民訴法――
一 一八九五年法に先立つ諸草案・法律
(1) 口頭主義・公開主義の採用/(2) 一八六二年の草案/(3) 一八六七年の草案/(4) 一八七三年の少額事件手続法/
(5) 一八七六年の草案
二 フランツ・クラインの出現
(1) 大学卒業まで――恩師アントン・メンガー――/(2) 司法省入省まえ/(3) 論文「未来」と司法省入り
三 一八九五年法の審議
(1) 「社会政策」の時代/(2) 帝国議会への提出/(3) 帝国議会での審議
四 一八九五年法の主な特色
(1) 受給権/(2) 準備手続/(3) 第一回期日/(4) 当事者一方の欠席/(5) 真実義務/(6) 訴訟指揮権/
(7) 口頭弁論調書とその法効果/(8) 更新権の制限
五 議会審議中のクラインの著作
(1) 「末来の訴訟における当事者代理」/(2) 『口頭主義の諸タイプ 一八九三年のオーストリア民訴法草案の判断のための資料』/
(3) 「オーストリアの新しい民訴諸法案」
六 ドイツ人からみたオーストリア新法案
(1) ベーアの「オーストリアの新しい民訴法」/(2) ヴァッハの『口頭主義――オーストリア民訴草案における――』/
(3) フィアーハウスの「オーストリア新民訴法案の議会での取扱い」
七 法施行の準備
八 法施行後のクラインの著作
(1) 『民訴実務に関する講義』/(2) 『訴訟における時代思潮』/(3) 『オーストリアの民事訴訟』
九 クラインの昇進
(1) 超速昇進/(2) 日本からの叙勲/(3) 大学の招へい
一〇 二度の司法大臣・総選挙・講和条約
(1) 二度の司法大臣/(2) 総選挙――「市民・民主」党/(3) 講和条約――サン・ジェルマンへの使節
一一 クラインの死去
一二 オーストリア法の外国への影響
一三 むすび
人物略伝
ISBN:9784797223644
。出版社:信山社
。判型:A5変
。ページ数:228ページ
。定価:4000円(本体)
。発行年月日:2016年01月
。発売日:2016年01月29日
。国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:LNAA。