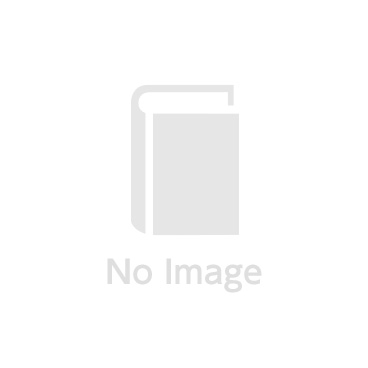どうしてこの国は「無言社会」となったのか
著:森 真一
内容紹介
電車で足を踏まれたのに無視されたことありませんか?
「無言社会」を考えることは社会のあり方を考えること。
すなわち社会観の問題である一方で、自分はどう生きるかを考えること、つまり人生観や人生論の問題でもある。
人生は社会に収まるものではない。人の誕生や死は、社会を超えるできごとだ。
だから、自分が 生きているこの社会を絶対視すること、社会の内部でだけ人生を考えることは、まるごとの自分の人生を考えるには、ふさわしくない。
そのためにも、普遍の視点、社会を超える視点、そして、社会の外部に出る視点が重要であることを伝えたい。
本書は学術書ではない。エッセイ風の読み物である。肩の凝らないように配慮しているつもりなので、気楽に読んでいただきたい。
(「はじめに」より)
※装丁:山口昌弘
第1章・「無言社会」という時代
何があっても無言な人々
ホンネはインターネットの中だけ
声を出す機械たち
ノリの悪いことはいえない
第2章・ 声を出さない理由
恥意識と「無言」
日本的男らしさと「無言」
秘の共有
やさしさに甘えて「無言」
集団への気づかいと「無言」
声を出すことの「重さ」
第3章・ これからも「無言」でやっていけるのか
あうん文化の限界
「無言ストレス」の発散としてのクレーマーたち
それでも社会は変われる
「線的」関係の基盤の動揺
「かまわれない自由」を優先する社会
「無言社会」への適応が招く不適応
集団嫌いの集団主義
「楽しさ」というつながる努力と工夫
「秘」の文化は守られるのか
第4章・「無言社会」を越えて
ほんとうは毎日が神秘で奇跡
社会というステージで役者になる
演技の自覚
答えを求めて、自分に問い続ける
私たちはみんな「何者でもない人(nobody)」
死を想い、社会を超える
声を出せなかった「コミュ障」の私 ~やや長いあとがき~
目次
第1章・「無言社会」という時代
何があっても無言な人々
ホンネはインターネットの中だけ
声を出す機械たち
ノリの悪いことはいえない
第2章・ 声を出さない理由
恥意識と「無言」
日本的男らしさと「無言」
秘の共有
やさしさに甘えて「無言」
集団への気づかいと「無言」
声を出すことの「重さ」
第3章・ これからも「無言」でやっていけるのか
あうん文化の限界
「無言ストレス」の発散としてのクレーマーたち
それでも社会は変われる
「線的」関係の基盤の動揺
「かまわれない自由」を優先する社会
「無言社会」への適応が招く不適応
集団嫌いの集団主義
「楽しさ」というつながる努力と工夫
「秘」の文化は守られるのか
第4章・「無言社会」を越えて
ほんとうは毎日が神秘で奇跡
社会というステージで役者になる
演技の自覚
答えを求めて、自分に問い続ける
私たちはみんな「何者でもない人(nobody)」
死を想い、社会を超える
声を出せなかった「コミュ障」の私 ~やや長いあとがき~
ISBN:9784782571033
。出版社:産学社
。判型:4-6
。ページ数:176ページ
。定価:1300円(本体)
。発行年月日:2012年12月
。発売日:2012年12月25日
。国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:JB。