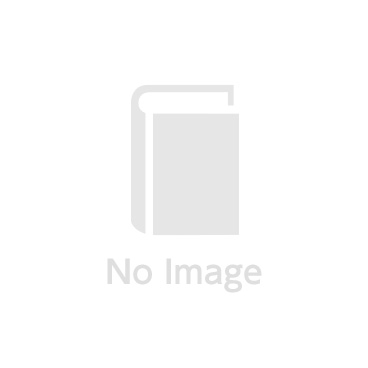現代組織論
著:田尾雅夫
内容紹介
わたしたちは組織を抜きに、経験せずして生きることはできない。組織と共にこの社会を生き抜く方法としての、新たな組織論決定版。
現代社会における組織とは何か。3.11、超高齢社会、グローバリゼーション──社会の仕組みが大きく変わりつつある今、向き合う知的な体系、学問も変わらざるを得ない。私企業のみを研究の中心としてきた従来の経営学を超え、政府、自治体、病院、福祉施設、労働組合、NPO等も対象とした、新しい体系を組織論第一人者が打ち立てる。
目次
はじめに
第1章 組織論の現在
1.組織とは何か
2.組織論とは何か
3.モダンの組織論
4.近代化,合理化,そして組織化
5.ビュロクラシ―の逆説
6.デモクラシーとの二人三脚
7.モダンの組織(ビュロクラシ―・システム)の動揺,批判,そして限界
8.ポスト・モダンの組織論
9.なぜポスト・モダン組織に至ったか
10.ポスト・モダン組織を超えて
第2章 組織デザイン
1.システムとしての組織
2.オープン・システムという前提
3.組織均衡
4.システムのための与件
5.組織とは何か
6.サイズ
7.肥大化と硬直化
8.ネットワークによるシステム構築
9.ネットワーク組織の限界
10.組織の多様性
11.要約
第3章 マネジメント─ビュロクラシーの効用と限界
1.その組織は,なぜそこにあるのか
2.ビュロクラシ―とは何か
3.ヒエラルキー構造
4.統制システム
5.管理者の役割
6.スタッフとライン
7.トップ・マネジメント
8.要約
第4章 起業と組織化
1.組織における運動の位置づけ
2.アソシエーション
3.アントレプレナー(起業家)
4.運動からの逸脱
5.組織化
6.組織化の経過
7.組織化以後
8.カリスマ
9.カリスマの限界と退場
10.要約
第5章 環境適合と戦略
1.環境と組織
2.境界
3.境界担当者
4.ルース・カップリング
5.環境
6.技術環境と政治環境
7.技術決定論の立場
8.タスク環境と一般環境
9.環境適合
10.戦略
11.戦略の限界
12.要約
第6章 制度,慣性,淘汰
1.制度とは何か
2.技術的環境との対比
3.理論的枠組み
4.慣性の法則
5.ポピュレーション・エコロジー(群生態学)の立場
6.批判的検討
7.淘汰
8.要約
第7章 組織における合理と非合理
1.合理性は成り立つか
2.ビュロクラシ―・システムの動揺
3.合理性を疑う
4.基本的な考え方
5.3つの視点の比較
6.合理性への疑念
7.人間という非合理
8.限定された合理性
9.散在する合理性
10.非合理の由来
11.行為モデル
12.ゴミ箱モデル
13.パワー論の立場
14.デザイン論の限界
15.合理性再考
16.要約
第8章 コミュニケーションと意思決定
1.コミュニケーション・モデル
2.伝達障害
3.コミュニケーション回路
4.インフォーマル・コミュニケーション
5.インターネット・コミュニケーション
6.意思決定
7.ルーティンと意思決定
8.合意形成は可能か
9.参加
10.意思決定過程
11.意思決定の工学
12.会議と委員会
13.意思決定の限界
14.意思決定の病理
15.要約
第9章 コンフリクトとパワー・ポリティクス
1.コンフリクトの由来
2.コンフリクトの評価
3.対人間コンフリクト
4.集団間コンフリクト
5.コンフリクト・マネジメントの実際
6.パワー関係
7.資源の確保
8.パワーゲーム・モデル
9.パワー・ポリティクス
10.パワー戦略
11.権威の賦与とポリティクスのルール化
12.組織間関係
13.要約
第10章 職場集団とリーダーシップ
1.集団の形成
2.職場集団
3.インフォーマル集団の働き
4.ホーソン研究
5.同調と逸脱
6.凝集性
7.非同調行動の出現
8.小集団の積極的活用
9.リーダーシップ
10.リーダー行動の構造
11.役割分化
12.状況適合
13.個性によるリーダーシップ
14.要約
第11章 社会化とコミットメント,日本的経営
1.組織人になる
2.適応と順化
3.社会化
4.メンバーシップ
5.不適応と過剰適応
6.コミットメント(自我関与)
7.コミットメントの3次元説
8.ローカルとコスモポリタン
9.組織文化の生成と対応
10.組織文化の成り立ち
11.組織文化と組織の成果
12.日本的経営
13.日本的経営とマネジメントの方式
14.企業戦士,そして会社人間
15.その限界,そして再評価
16.要約
第12章 人的資源管理
1.人的資源とは
2.個人差
3.報酬システムの構造
4.キャリア
5.キャリアの高原状態(プラトー)
6.キャリアの限界
7.ピーターの無能の法則
8.モチベーション
9.ストレス管理
10.人的資源管理
11.人的資源管理の実際
12.要約
第13章 サービスとプロフェッショナル
1.サービスとは何か
2.送り手と受け手
3.クライエント
4.サービス組織とは
5.ヒューマン・プロセッシング
6.トータル・インスティテュート
7.共感の逆説
8.ストリート・レベルのビュロクラシー
9.マネジメントの限界
10.知識の管理
11.プロフェッショナリズム
12.プロフェッションの要件
13.プロフェッションの階層性
14.専門職化(プロフェッショナリゼーション)
15.実践的な対応,あるいは即時即決的な対応
16.要約
第14章 組織と倫理
1.組織の倫理とは
2.ガバナンス
3.組織の犯罪
4.ビュロ・フィロソフィ
5.個人としての倫理
6.反社会的行動
7.組織市民行動
8.不満分子とは
9.内部告発
10.告発過程
11.革新者になる場合
12.組織と市民道徳
13.要約
第15章 組織の病理
1.倫理と病理
2.ビュロクラシーの病理
3.パワー・ポリティクスの過剰
4.ルーモア・ポリティクス
5.組織の中の軽犯罪
6.差別
7.フラストレーション仮説による説明
8.個性に由来する組織の病理
9.職場のモンスター
10.マキアベリズム
11.自己愛による破綻
12.サイコパス
13.カリスマの暴走
14.要約
第16章 組織の革新
1.変革,変化,そして順応
2.変化への抵抗
3.パフォーマンス・ギャップの認知
4.変革過程
5.組織文化の革新
6.変革と変化における許容能力
7.組織学習
8.低次学習と高次学習
9.ダブル・ループ学習
10.組織学習の限界
11.革新の担い手,またはチェンジ・エージェント
12.変化における成功条件
13.要約
第17章 評価論とその限界
1.組織スラック
2.スラック概念の拡張
3.よくマネジメントされている組織とは
4.評価における合理性
5.資源活用
6.社会的な評価
7.サービスの評価
8.評価尺度の必要性の再確認
9.代理尺度
10.評価の活用
11.正当性という基準
12.名声という評価
13.存続という評価
14.アカウンタビリティ
15.要約
第18章 一つの結論
引用文献
著者略歴
1946年香川県に生まれる.
京都大学文学研究科(心理学専攻)修了,博士(京都大学,経済学),京都府立大学文学部社会福祉学科助教授,京都大学経済学部経営学科教授,京都大学公共政策大学院教授を経て,2008年以降,現職.
現在愛知学院大学経営学部教授.
著書『行政サービスの組織と管理』(木鐸社,1990年,日本経済新聞経済図書文化賞,日本組織学会賞を受賞),『組織論』(共著,有斐閣,1998年),『組織の心理学』(有斐閣,1999年),『自治体の人材マネジメント』(学陽書房,2007年),『セルフヘルプ社会』(有斐閣,2007年,日本社会心理学会賞),『公共経営論』(木鐸社,2010年)『市民参加の行政学』(法律文化社,2011年)など.